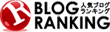「……うつ伏せのまま全身を切り裂かれるという遺体が寝室で発見されました」
暗闇のなか浮かび上がるようにキャスターが淡々としゃべっている。
「こちらが現場の映像です……」
その薄明かりに照らされながら、数人がその映像を眺めていた。その誰もがそれぞれにおぞましさを表情からにじませていた。顔を背ける者もいた。
僕はまじまじと見つめていた。魅入っていると言ってもよかった。
<なんかおれ、足出てんなぁ~……>
なんとなくそんなことがぼんやりと脳裏をよぎった。
<……“いる”>
突然、バサバサバサっと布団が激しく波打った。
ほとんど本能的だった。布団に隠れていなかった両手の3本の指だけで、足元のほうへと荒れるように引っ張られる布団をしっかりとつかんだ。
パニックという奔流が、あっという間に全身を覆った。肌があわ立つのが自分でもわかった。
声も出ない。
夜の沈黙のなかで、まるで嵐にあおられたようたような音が耳もとで衝撃をともなって鳴り止まない。そしてそれは、さらに激しく荒くなっていく。
しがみついた6本の指が折れそうだった。
あらん限りの力を込めて目を閉じた。
が、それは、さっき目に焼きついた映像を蘇らせるだけだった。
<やめてくれ!>
恐怖と焦りが体のなかで沸騰する。
<やめてくれ!!>
ふたたび目を開けると、そこには淡い夜の明かりに照らされたいつもの光景がある。うつ伏せで首だけを曲げて横に向けていた先には、ただ無機質に浮かびあがる日常があった。クッションと枕が交互に重なっていた。
しかし、それが余計に恐怖をあおった。
間違いなくこれは、現実なのだ。
まるで硬直したかのように込めている6本の指先への力も、全身が凍りついたように小刻みに震えながら動かすことができないのも、耳や後頭部にぶつかってくる風圧も、それらすべてがはっきりと意識のなかに飛び込んできていた。
肩越しの視界の隅では、死ぬ間際の魚のように黒い布団が暴れていた。その音は断末魔の叫びのようだった。
しかしそれは、明らかに、女だった。もし男がこれだけの必死さをもって力をこめれば、たった6本の指でそれに抗うことは不可能だった。
6本のうちの1本が、布団からはずれた。
そのときだった。全身の血液が静かなさざ波のように足元へスーッと引いていくのがわかった。吸い込まれるようでもあった。
ずっと指をその激しさで振り払おうとするかのような荒さだったのが、今度は、しっかりとつかみ、そちらへと飲みこむようにたぐり寄せ始めたのだ。
すぐ前にあったクッションがより大きく見えていくのは、それだけ目が見開かれたということだったのだろう。
音もなく指がちぎれていくようだった。
さっきはずれたのは、左手の中指だった。そして今、右手の中指が耳もとでバリッと弾けた。
きつく目を閉じ、出せるだけの力をそこに集中させた。布団から放れた指を戻すことはできず、右左2本ずつの指で抵抗するのがやっとだった。
汗ばんだ親指の腹が生地とこすれてギリギリと音を立てている。
<やめてくれ……やめてくれ……>
まるで呪詛のように、それだけを心のなかで繰り返していた。一語一語、確認するような言葉とは裏腹に、今にも破裂しそうな心臓の警鐘を聞きながら。
<やめてくれ……お願いだから、やめてくれ……>
すると、それまで足元へと引っ張られていた力が、まるでそこに漂う空気のなかへとにじんでいくかのように消えていった。
と同時に、全身からドッと汗がにじんだ。体の奥に垂らした一滴がどんどん大きくふくらんで、噴き出す手前の瞬間に破裂したようだった。
胸の下でシーツが湿っていくのが、はっきりとわかった。
もう6本の指先は感覚が麻痺していた。動かすことすらできなかった。
反対側を向いて、頭上にある窓から漏れてくる夜の明かりに照らされた目覚まし時計の時間を見た。
7時43分。
<まだ早い>
バイトは12時からだ。
ついでにもう一度首をまわして、足元を確認しようとしたが、全身に広がる恐怖がそれを妨げたようだった。
今、耳に聞こえてくるのは、目覚まし時計の規則正しい秒針の音だけだった。
意味もなく、頭のなかでそれを数えはじめた。
そうして、ただひたすら頭上の窓の向こうで、車のドアがバタンと閉まる音が聞こえてくるのを待っていた。そう、目の前の闇に毒づきながら。
<なんで今日に限って帰ってこねぇ~……>
安堵なのか、その余韻なのか、そこで初めて深呼吸をしてみた。
たとえ浅くとも、吸えるだけの息を吸い、それを吐いていった。
が、しかし、途中でそれは止まった。
そう、首をまわすことができなかったのは、恐怖でも何でもなかったのだ。まだ“続き”があったのだ。
右の太ももの裏に、衝撃があった。
そして、呼吸を忘れた。
すぐに腰の少し上あたりに、“手”を感じた。今度はそれと反対側の少し下に左手、最後に、左のふくらはぎに最初と同じ重みを感じた。
全身がベッドに沈んだ。
さらに力が込められ、筋肉がちぎれそうで思いっきり叫びたかった。しかし、声は出せなかった。
<やめてくれ……消えてくれ……消えてくれ……>
背中から右手が消えた。
眼球だけが目覚まし時計とシーツのあいだで激しく揺れた。
秒針が音もなく1秒進んだと同時に、離れた右手が肩の上に触れた。
布団がカサッと音を立てたその瞬間、足の激痛がどこかへ消えた。
全身が総毛立ち、ゆっくりと太ももから離れた重みが右のわき腹に沈んでそこでバキッと音を立てたとき、頭のなかと体の血のめぐりが乱れたような感覚に陥った。
そして、それから左の尻の上に円形のじわりとした重みを感じてから、静かに太ももまで伸びていった細長い感触を受けたときには、忙しない眼球の動きで酔いそうになっていた。
左手は、その下にある腰を布団の上からさらに強く圧迫していた。さらにその内側にある内蔵をもにぎりつぶさんばかりだった。
動けない。
声も出せない。
両目からなにかが噴き出しそうになっていた。
すでに右目だけでしか見れなくなった目覚まし時計の秒針の音だけが聞こえてくる。
布団が背後でガサガサとわずかな音を立てた。左手が爪痕を残すようにそこから離れたとき、やっとわずかな息が吸えた。
と同時に一瞬視界が白く弾け、眼球は見開かれたまま呼吸とともに凍りついた。
えぐれられた右目には、遠近感のずれた目覚まし時計が歪んでいた。
聞こえてくるのは、自分のものなのかすらわからない速すぎる鼓動と、耳なりだけだった。
上から頭を押さえつけられているのだ。
右耳のあたり一帯を鷲づかみにするような細い手を感じたその瞬間、ベッドにたたきつけられたかのように埋もれた顔の左半分で、一瞬前に吸い込めたその息を飲み込んだ。
心臓は血液というより、必死になって酸素を送っているようだ。両腕、両足をただ伸ばしたうつ伏せのまま指先1つ動かせない。冷や汗すらにじんでこない。
この状況を脱するための思考も何もなく、ただただ発狂寸前だった。
呼吸も浅く、喘ぎのなかで感じるだけのわずかな空気だけだった。
ベッドを軋ませながら、さらに両手が圧迫してくる。またあばらに穴をあけるような音がした。
その激痛には、目をつぶる以外できなかった。口を開けても喉に今にもはちきれそうな太い血管を浮かび上がらせるだけだった。
<やめてくれ……消えてくれ……頼むから消えてくれ……>
とそのとき、窓の向こうで音がした。
それから玄関の鍵が開いた。階下で居間のドアが開き、やがてテレビの音も聞こえてきた。
が、動けるようになったわけではなかった。まだベッドに押さえつけられたままだった。むしろ、さらに深く沈んでいくようだった。
その安堵感は、それと同じだけ恐怖も広げていった。
それからシャンプードレッサーが水を噴き出し、それが止まると、階段の電気のスイッチを入れるカチッという音がした。
階段を上がってくる。
それでも目が開かない。さらにその手が右から押さえつけてくる。
部屋のドアが開き、電気がついた。こちらのドアの隙間にも、その光が漏れてきた。
右目の横がメリメリと音を立て、体の左側でくぼんでベッドが軋んだ。わき腹から重みが去った。
<頼む、消えてくれ……消えてくれ……>
ドアの向こうでは、階段を下りていく音がしていた。
<オイ!! 気づけよ、コラ!! 下りてく前にドアを開け……>
わき腹から離れた足は、そのまま体の横に伸びた右腕を土踏まずのところでしっかりと踏みつけた。と同時に、押さえつける両手の力が一瞬やわらいだ。
<やめてくれ……>
吸いこんだ息が震えていた。さらにきつく目を閉じた。
<………>
自分の心のなかとはいえ、なにを叫んだのかもわからない。
闇のなかで音が消えた。
そして、背後からの手の重みも消えた。
それでもしばらくは、微動だにできなかった。
やがて、ふたたび目を開けたとき、時計が少し傾いて動いていた。
が、その奥にある少しへこんだスペースは、なぜか理由もなく見てはいけないと、すぐにクッションと枕のあるほうへ顔を背けた。
が、それらを見れたのは、一瞬目の前に長い黒髪が垂れたあとでだった。
とにかく呼吸がしたかった。
震えながら息を吸い、吐いた。
そのときになってやっと、実際に自分の意思で自分の体を動かせるようになったのだ。
とりあえず、そのときははみ出していた両足を、布団を持ち上げて隠した。
それから指先を少し動かしてみたり、布団のなかでTシャツの濡れ具合を確認したりした。
しかし、まだ上体を起こす気にも、首をまわす気にもなれなかった。
ふたたびドアの向こうで階段を上ってくる音が聞こえてきた。
言い知れぬ安堵が全身に広がった。
意を決して足元を確認しようとしたが、それでもまだできなかった。
一つ息をついてから、その前にカーテンを開けた。
そこに映ったらどうしようと、見れなかった。
またひと呼吸ついてから、窓のなかに目を向けた。
<………>
一瞬、言葉を失った。
<……いつもどおりだ>
窓の向こうには、向かいの家の居間と、2階の窓に明かりがあった。
そのあたり前のようにある“いつもどおり”が、こんなにも安心感を与えると、改めて知った。
背後を振り返り、そこにも同じいつもどおりの光景を見た。
半分だけ開けてあるクロゼットの扉、外光に浮かぶ電気のスイッチ、ギターケース、壁、ドアの下から漏れるやわらかな明かり、そしてその向こうへと続くドア。
それらを1つ1つ確認してから、また布団のなかに潜った。
時間はもう気にしなかった。
目を閉じると、自然と布団のなかで体が小さくなっていた。
そして、バイト先の玄関の前で、ひとり煙草を吸いながら、そんなことを思いだして見上げた月は、満月だった。
……もうこれで2回目だ。
いい加減、ウメちゃんの冷たさにやられるばかりさ。
「んなこと知るか!!」
……とか何とか言われそうなもんだけど、気づけ。アホか。ソウル・メイトなら、GBみたいに“キュピーン”ってなりやがれ。
まあ、それはいいにしろ、いやぁ~しかし……
これぞまさに“アバリアリティ”というやつなんだろうか??
うん、“いる”って感じたとき、間違いなく“いた”のだ。そう、そこには1%の疑念もなかった……
もしかしたら、ついに“ドミネータ”になったのか??
あるいは、やっぱし俺様、子供なのか??
拝啓 ウメちゃんへ
もうさすがに2回目です。
今回の金縛りにしろ、前回のものしろ、
パソコンの電源が勝手にブイーンと
ついてみたり……
うん、たぶんおかしいです。
僕に霊感なんてありません。
まだはっきりと「見た」ってことも
ありません。
んまあ、見てしまったらそのときは
間違いなく気が狂うかもしれません。
今回、危うく赤屍さんに刻まれそう
でした。
追伸 もずくは“りんご酢”のほうがオススメです。
さらなる追伸 内輪話でごめんなさい。
とまあ、ちょっとした解説とするとだな??
要は、俗に言う“金縛り”ってやつだろうな……
んで、“<……“いる”>”っていうところまでが、ホンマもんの“夢”ってな感じだったわけよ。
完全に「見てた」から。
しかもあのニュースは、数人でそのテレビを囲んでたわけだ。
だれかはわからない。
ただ、保育園の先生みたいな女の人と、子供が2人と、スーツを着た男の人が1人いた。あとは見えなかったか、いなかった……
あとはもう、実感としてあった部分……間違いなく現実だろうな。
そう、それはなぜなら……
両手の指3本、つまりは布団に隠れてなかった部分に嵐に見舞われたような痛みがあり、抜け出たとき布団には、はっきりと人がつかんだような手形が残っていたのだから。
- October 28, 2004 1:40 AM
- [ 夢 ]