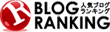僕は歩く。
とにかくずっと歩きつづける。
道はない。景色もない。
なにもない場所をただずっと歩きつづけた。
向こうから男が一人やって来た。
見知らぬ男だ。中肉中背の背の高い帽子をかぶり、その端からはみ出している髪の毛はボサボサで、縁の太い汚いレンズの眼鏡をかけている。
見るからに汚らしい乞食のようなオッサンだ。
「今何時?」
その男がすれ違いざまに話しかけてきた。顔もこちらに向けてはいない。
僕は思わず立ち止まった。
「は?」
その男も立ち止まった。
「ほら、じゃあこの時計やるよ」
「は?」
「いいから持ってけ」
黄ばんだ乱杭歯をむきだしに笑いながら、男は強引に僕の腕を引っ張ってその腕時計を貼り付けた。
「じゃな」
男は僕のうしろを歩いて行った。
僕は腕時計に視線を落とす。
プラスチックなのか硝子なのか、その時計の時間を見る部分には大きなヒビが入っていた。八時から一時に向かって伸びている。
鼻を近づける。
魚の目玉にカビが生えたようなにおいがした。
頭痛がする。
よく見れば、その腕時計は止まっていた。
だが、不思議とはずそうとは思わなかった。
僕はまた歩き始める。
遠くに海が見えた。
僕の足は間違いなくそちらに向いている。
なんら魅力は感じない。
海はもう見飽きてる。
どこの、どの海に行っても、結局海は海でしかない。
波が立って、潮の香りが充満していて、そこに夕陽が沈めば儲けもんっていうぐらい。砂浜かゴツゴツした石か。それぐらいの違いしかない。
磯の景色が急に開けた。漣が静かに寄せては引いていく。
右手には古びた藁葺きのような小屋があって、左手には枯れた水道がある。井戸もある。
僕は海に向かって歩きだす。
だけど海には着かなかった。
きっとまだ明けてない朝だ。乳白色の靄があたり一面を覆う森のなかに僕は立っている。
足元を見てそこをたどろうとしても、自分の足跡すら見当たらない。
腕時計がおかしかった。
あからさまに時間が戻っている。
それとも自分がその時間に戻っただけなのか?
頭痛がする。こめかみの上、目尻の真横が、ちり紙が燃えていくように痛む。
しばらくのあいだ目を閉じていた。
傷みがすーっと消えていくようだった。それがなんだか心地よかった。
足を踏み出そうとしたそのとき、僕はその足を宙に浮かせたまま止めた。
僕の足と同時に、腕時計も進みだそうとしたからだ。
実際に進んだわけじゃない。見たわけでもない。
でも、なんとなく体のなかのなにかがそう感じた。
また足を元の位置に戻す。
腕時計は止まったままだった。
一歩だけ足を前へ出した。
腕時計の針も一秒だけ進んだ。
もう一歩足を前へ。
また腕時計が一秒進んだ。
逆に。
僕は日照りの強い坂道をゼエゼエ息を切らしながらも、一生懸命昇っている。
僕が足を差し出すたびに、腕時計は逆に一秒戻っている。
この坂道もおかしい。いつまで経っても頂上が見えてこない。
誰かがグルグルとまわしつづけている商店街の福引の機械の上を歩いているようだった。
たいして深くも考えず、僕は地球の円さを呪った。
そういえば煙草を吸っていない。
僕は煙草に火をつける。
ひと吸いだけですぐ捨てた。
息切れがひどくて疲れているときほど煙草を欲しがるもんだけど、そういうときほど煙草のマズさに嫌気が差す。
僕はまだ歩きつづける。
薄暗い。いや、薄明るい。
井戸のなかにいるみたいだ。
わずかに見える隙間では、まるで蝿のように人がすれ違ってる。
ビルの谷間だ。
だからだろう。余計に早い。早送りで見ているようだ。
蒸し暑い。
あまりに窮屈で変な汗もかいてきた。
僕は外へ飛び出した。
人間が普通に歩いている。
こちらに向かってくる。あっちへ向かって行く。
ちゃんと前向きに歩いてる。
でも、僕が進めば時計は戻る。
そうだ。
テレビの見すぎだ。実際に時間が戻ったところで、人間がうしろ向きに歩くわけじゃない。
現実としてそれを目の当たりにした人がそういう映画を作ったわけじゃない。時間が戻るんだから、きっとそうなるんだろうっていう憶測のもとに、映像としてそうしただけに過ぎない。
しょうもない。
僕は素っ裸で雑踏のなかを歩きだした。
暗い。
さっきのビルの谷間よりもっと暗い。
そういえばさっきも暗かった。
僕はあのとき、隙間の隙間にいたんだろうか?
それとも僕自身が隙間だったんだろうか?
突然なにかにぶつかった。
「なにやってんの?」
見上げると、不自然に黒い髪の女がこちらを見下ろしていた。
六四ぐらいで二つに分けた長い髪の片方が、高そうなTシャツの襟からなかに入っている。腰ぐらいまでありそうだ。高そうなピアス。高そうなサングラス。高そうなネックレス。高そうな乳。だけどダッサいキュロット姿。そしてドギツい原色のビーチサンダル。
「別に」
「フルチンでぶつかっといて"別に"はないんじゃない?」
「すまん」
すると女は微笑んだ。
僕に手を差し伸べて起き上がらせてくれた。おまけに尻や背中をかるくはたいてくれた。
「わりぃ」
「いいよそんな。チンポの一本や二本、別にめずらしいもんじゃないし」
「おまえ、おもしれぇな」
女は声を出さずに笑った。
「おまえもな」
そこで夢は終わった。
「ワオ」って言って起きた。
ビビッた。
結局、腕時計はなんの役にも立ってないような気もしないでもない。
もう少し夢の向こう側にいれば、なんかの役に立ったのかもしれん。
俺様はこんな夢をよく見ておる。
- June 23, 2007 12:28 AM
- [ ゲロ古 ]